�N���X�^�j���E�h�i���G���̓������{�Ѓz�[���y�[�W
2008�N5����
![[���W]2008�N�ŐV�̂�����](imgs2008/2008_05/news0805_01.gif)
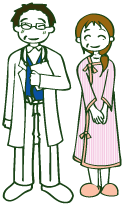
���{�̎��S�����g�b�v���߂邪��B
���A����͑��������ł��鎞��B
���ÂɊւ��Ă��ŐV�Z�p�����A�ǂ�ǂ�a�C�ւƔF������Ă���B
���ł��A�늳���̍����݂���̎��Ö@�ɒ��ڂ��Ă݂��B
��Ȃ����Â��ł���݂���̍ŐV���Ö@
�@�늳���A���S���A���ɍ����݂���B���݁A�݂��Â̑I�������L�����Ă��Ă���B
����̐i�s�╔�ʁA�[���Ȃǂɂ��A�ł�����@���قȂ邪�A�炸�Ɏ��Âł����������p������B
�@�܂��A�ߔN�����Ă������o����p�ȂǂӂƂ���a�@�����邽�߁A�a�@�̕��j���������Ȃ���A���Â̑I��������̂��]�܂����B
�����o����p�Ƃ�
�������J�����A�Pcm���̌����J���A���������p����}�����Ĉ݂�؏�������@�B���҂̕��S�����Ȃ��A�������B
�����������ÂƂ�
���������݂̔S���ɂƂǂ܂��Ă���ꍇ�ɍs���鎡�ÁB�������J�������A���Ȃōs����B�݃J�������f�Ɠ����悤�ɁA��������������݂ɓ���A���Ê����g���Ă������菜���B
| �� �݂���̓��������Õ��@ �� �u�d�r�c�v�Ɓu�d�l�q�v��2��ނ�����B |
|---|
| �d�r�c ���܂��܂Ȏ�ނ̓d�C���X���g���Ĉ݂̕\�ʂ�蔍�������@�B ���_��A�ǂ�ȑ傫���̑g�D�ɂ����Â��s����̂������B |
| �d�l�q �X�l�A�ƌĂ������̗ւ�a�ϕ��Ɉ��������A�����g�d���𗬂��Đ�����@�B ��2cm�܂ł̑����݂��ΏہB��r�I�Z���ԂŎ��Âł���̂������B |
�����K���̌������ŗ\�h�B���f�ő����鑁������̔����B
�@����͐����K���̉��P�ŗ\�h�ł���a�C���Ƃ���Ă���B
�i�����T���A���������݉߂��Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ͂������A�H�����ɂ��H�v���K�v�B�畆����\�h�̂��߂ɁA���O���𗁂т����Ȃ����Ƃ���B
�\�h���Ȃ���A���������ɓw�߂�ƋS�ɋ��_�B���o�ǏȂ��Ă��A�N�ɂP�x�̌��f��ϋɓI�Ɏ����B
�@�Ⴆ�A�݂��f�A�咰���f�A�x���f�A�����f�Ȃǂ͂S�O�Έȏ�̐l�ɁA�q�{�z���f�͂Q�O�Έȏ�̏����Ɍ��f�����߂��Ă���B
���ʂɂ���Ă͓������ɂ�錟�f������悤�ɂȂ��Ă���B
�@�܂��A����͎���a�C�ɂȂ���邱�Ƃ��m���ė~�����B�������������Â̑I�������L���A���������ÂȂǂő̂ɕ��S���������Ɏ��Â��ł��镔�ʁA�ꍇ������B
���̂��߁A����I�Ȍ��f�͂������A�C�ɂȂ�Ǐ����ꍇ�͎�f���邱�Ƃ��A�����Ȃ����ƂɂȂ�B
�@�����Ƃ������́A�厡��̐�����ǂ������A�K�v�ł���Z�J���h�I�s�j�I���i�厡��ȊO����̐���ɑ��k���邱�Ɓj���s���A�ŐV�̂��Ï��Č��C�ȑ̂����߂������B
| �H�����ł���\�h |
|---|
| ���h�{�o�����X�̂Ƃꂽ�H�������� �����b���T���A�H�߂���h�~���� ���r�^�~���ƐH���@�ۂ�ϋɓI�ɂƂ� �����h�����̂�M��������͔̂����� ���ł��������A�J�r�̐��������͔̂����� |
| ����\�h�Ɏ����ꂽ���h�{�f |
| �r�^�~��A�E�r�^�~��C�E�r�^�~��E�E�H���@�� �����ł��A��J�����[�Ńr�^�~�����H���@�ۂ��L�x�ȁg���̂��h�͂��ЁA�H��Ɏ����ꂽ���B�R�����p�Œ��ڂ���Ă�����O���J�����܂ގ�ނ̂��̂��������B |

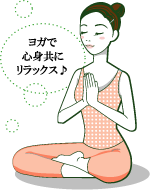
����Љ���鎄�����́A���X�̐����̒��ŁA�m�炸�m�炸�̂����ɁA�l�̂Ɉ��e�����y�ڂ����w�������̓��ɒ~�ς���A�܂����g�̑̓��ł͊����_�f�ȂǁA�זE�������ĘV���̌����ƂȂ镨������������Ă��܂��B
�f�g�b�N�X�Ƃ́A�T�v�������g�̐ێ������A�^���ȂǂŁA�̓��ɗ��܂����őf��r�o��������@�B�ŋ߂ł͔��e�E�_�C�G�b�g��a�C�̎��Âɂ����p����A�V����̌��N�@�Ƃ��đ�ϊS���W�߂Ă��܂��B
�h���֔�ɂ̓f�g�b�N�X����������
�����̒���A������A���ɁA����ɂ́A���r��ɐ����o���A�C���C�����c�B����͕֔�Œ����ɕւ����܂鎖�ɂ���Ĉ��ʋۂ������A�̓��ɓőf���T���U�炵�Ă���̂ł��B���ʋۂ͒����ŕ��s�������o���A�̂Ɉ��e����^���܂��B�V��ӂ������Ȃ�A�_�C�G�b�g�����Ă��Ȃ��Ȃ������Ȃ��g�̂ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�f�g�b�N�X�u��Łv���s����|�C���g�́A�܂��r�o�A���Ȃ킿�ւƔA�Ȃ̂ł��B����ő̓��̓őf�̂X�O���ȏ��r�o�ł���̂ł��B�֔�����C�R�[���őf�̗��ߍ��݉����ɂȂ���̂ł��B�܂�f�g�b�N�X�ɂ���āA��茒�N�I�Ȑg�̂����グ�鎖�ɋ߂Â��̂ł��B
�ւ�A���̓��ɂƂǂ܂��Ă��鎞�Ԃ�������Β����قǁA�]���ȓőf���̓��ɂ��鎞�Ԃ������Ȃ��Ă��܂��܂��B�֔�̓f�g�b�N�X�̑�G�I�����̋K���������r�o��S�����������̂ł��B
�܂��͐������Y���i�r�փ��Y���j�𐮂��悤

�K����������������Ƃ͂����Ă��A������ӂ܂łƍl����ƁA�Ȃ������Ɏv���Ă��܂����������ł��傤�B
�Ȃ���߂Ĕr�֏K�������ł��g�ɂ��Ă݂Ă͂������ł��傤���B���̎��Ԃ̓g�C���ɍs�����Ԃ��Ƒ̂ɔF�������鎖�ŁA���R�Ɣr�ւ�������鐶���K�����g�ɂ��̂ł��B
�������A���̂��߂ɂ͈��̎��ԂɐH��������Ȃǂ̏������K�v�ƂȂ�ł��傤�B�܂��͂��ꂪ���N�̂ւ̑����ł��B���������Ă݂܂��傤�B
�H���@�ۂ��ݒ��̓����𐳏퉻
�֔�̌����Ƃ��Ă͗l�X�ȗ��R���������܂����A��͂菬�H��A���H���Ă��܂����Ƃ͗ǂ��Ȃ��悤�ł��B���R�A�ւ͐H�ו��������܂��̂ŁA�H�ׂȂ����Ƃ͈݂⒰�̃X���[�Y�ȓ�����W�Q���Ă��܂��܂��B�܂��͂�������H�ׂāA������ƈݒ������邱�Ƃ���ł��B
�����ĉ���H�ׂ邩���d�v�ł��B���ɕւ��炩�����Ē����h�����A�X���[�Y�Ȕr�ւ𑣂�����A�����̑P�ʋۂ𑝂₵�Ē������𐮂��Ă����̂��H���@�ۂł��B �����̐ێ��S�����܂��傤�B
���_�ʂ��炭��e��
����̓X�g���X���������̒��ƌ����܂����A���̓X�g���X���鎖�ɂ���āA�����_�o�̃o�����X������Ă��܂��܂��B ����ɂ���ċN����֔���u������֔�v�Ƃ����܂��B
�܂��A�u�K�����֔�v�́A�䖝���邱�Ƃ��J��Ԃ��ƋN����܂��B�ֈӂ��䖝��������ƁA�ֈӂ�`����h�����]�ɓ͂��Ȃ��Ȃ�܂��B�䖝���Ȃ��ł����Ƀg�C���ɍs���悤�ȏK�������܂��傤�B
�^���s�����������悤
���̓������h��������A�������肷����@�̈�ɉ^�����������߂ł��B���ł��ȒP�ɂł��郈�K�Ȃǂ��ǂ��ł��傤�B
�Ⴆ�A�����ڊo�߂����ɑ����グ��B���̎��ɁA�ܐ���Ȃ�����A�L�����肷��Ɨǂ��ł��傤�B����ɁA���̑������E�ɓ|���A�����������f���ƁA�����b�N�X���Ȃ��環�Ɏh����^���鎖���ł���̂ł��B
�����A����L���ďグ�邱�Ƃ��ł��Ȃ���A�G�𗧂Ă邾���ł��ǂ��ł��傤�B���Ă��ЕG�����E�ɓ|���Ȃ��瑧��f���Ƃ������˂����̂ŁA�����h������܂��B
�܂��A�َ��̃|�[�Y�i�K�X�����̃|�[�Y�j���ǂ��ł��傤�B�����ɂȂ��āA���G��������ނ����̂���y�ȃ��K���������߂ł��B����̋C�����ǂ��X�^�[�g�ɁA��x�S�����Ă݂Ă͂������ł��傤���B
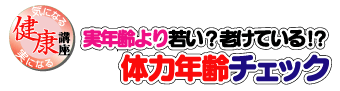
���܂ł����C�ł������Ȃ�A�̗͂����Ă������ƁB���퐶���Łu����H�v�Ɗ�������܂��́A�̗͔N��`�F�b�N�B���N���ێ����Ă��������Ƃ�����炵�𑗂�܂��傤�B
���C�Ŏ�X�������邽�߂�
�ŋ߁A�K�i����C�ɋ삯�オ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����A���������������ő��ꂪ����A�̂��v���悤�ɓ����Ȃ��ȂǁA�^���\�͂�̗͂̒ቺ�ɐS������͂���܂��B
�l�Ԃ̗̑͂͂Q�O����s�[�N�Ɍ}���A���̌�͐����Ă����܂��B ���i����^�����邱�Ƃ�S�����Ă����Ȃ��ƁA�̗͂͂ǂ�ǂ�ቺ���Ă����܂��B�N��Ƌ��ɐ߁X�̒ɂ݂������̂́A�ؗ͂�߂̏_�炩���������Ă��邽�߂ł��B
�����̔N��ɑ��������̗͂��ێ��ł��Ă���̂��C�ɂȂ�Ƃ���ł��B�܂��͎����̗̑͂��ĔF�����邽�߂ɂ��A�̗͔N����`�F�b�N���Ă݂܂��傤�B���Ȑf�f���ł��܂����A���݁A�X�|�[�c�W����E��A��ǂȂǂ��܂��܂ȏꏊ�ő̗͐f�f�ł���ꏊ�������Ă��܂��B���Ƃ̎w��������A����̉^�����@�ɂ��Ă��A�h�o�C�X���Ă��炦��ł��傤�B
��Ȃ��Ƃ́A�����̗͔̑N�����������Ɣc�����āA�����ɍ������̗͂Â�������H���邱�ƁB�^���K�������A���^�{���b�N�V���h���[���̗\�h�E���P�ɂ��Ȃ���܂��B����҂ɂƂ��ẮA�̗͂������ƂŐQ�������h�~���邱�Ƃ��ł��܂��B
���̗̓e�X�g�̃v���O����
| �v���O���� | 20�Α� �i�����ҁj |
20�Α� | |||
|---|---|---|---|---|---|
| �j�� | ���� | �j�� | ���� | ||
| �@�������܂܃W�����v�B �ǂ̂��炢�̋����ׂ�H �i�����Ă���Ƃ��̂ܐ悩��A����̂����Ƃ܂Łj |
 |
250cm �ȏ� |
170cm �ȏ� |
230�` 249cm |
150�` 169cm |
| �A�Е��̑��ŗ����A�ڂ��J�����ɁA ���b�������ɂ�����H |
 |
90�b �ȏ� |
80�b �ȏ� |
70�` 89�b |
70�` 79�b |
| �B�����őO�㍶�E�ɉ��ׂ�H �i10�b�ԁj |
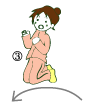 |
30�� �ȏ� |
26�� �ȏ� |
25�` 29�� |
23�` 25�� |
| �C�r���ĕ���������ł���H �i2�b��1��̃y�[�X�Łj |
 |
29�� �ȏ� |
11�� �ȏ� |
21�` 28�� |
8�` 10�� |
| �D�傫�������z���ĉ��b�~�߂���H |  |
33�b �ȏ� |
20�b �ȏ� |
29�` 32�b |
18�` 19�� |
| �E�����đO�������Ƃ��A�����ǂ��܂œ͂��H �i�ő�3�b�ԃL�[�v�j |
 |
16cm �ȏ� |
19cm �ȏ� |
12�` 15cm |
16�` 18cm |
| �v���O���� | 30�Α� | 40�Α� | 50�Α� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| �j�� | ���� | �j�� | ���� | �j�� | ���� | |
| �@�������܂܃W�����v�B �ǂ̂��炢�̋����ׂ�H �i�����Ă���Ƃ��̂ܐ悩��A����̂����Ƃ܂Łj |
215�` 229cm |
130�` 149cm |
190�` 214cm |
110�` 129cm |
1�` 189cm |
1�` 109cm |
| �A�Е��̑��ŗ����A�ڂ��J�����ɁA ���b�������ɂ�����H |
50�` 69�b |
50�` 69�b |
31�` 49�b |
31�` 49�b |
0�` 30�b |
0�` 30�b |
| �B�����őO�㍶�E�ɉ��ׂ�H �i10�b�ԁj |
22�` 24�� |
19�` 22�� |
18�` 21�� |
16�` 18�� |
1�` 17�� |
1�` 15�� |
| �C�r���ĕ���������ł���H �i2�b��1��̃y�[�X�Łj |
16�` 20�� |
6�` 7�� |
11�` 15�� |
4�` 5�� |
0�` 10�� |
0�` 3�� |
| �D�傫�������z���ĉ��b�~�߂���H | 24�` 28�b |
16�` 17�b |
19�` 23�b |
13�` 15�b |
1�` 18�b |
1�` 12�b |
| �E�����đO�������Ƃ��A�����ǂ��܂œ͂��H �i�ő�3�b�ԃL�[�v�j |
9�` 11cm |
13�` 5cm |
6�` 8cm |
9�` 12cm |
0�` 5cm |
0�` 8cm |
�Q�l�����^�u�̗̓e�X�g�̃v���O�����v�i���N�E�̗͂Â��莖�ƍ��c���s�j
�̗͂Â���́A�����Ȃ������̒��Ɏ������
�̗͂����邽�߂ɂ́A�^���K����g�ɂ��邱�Ƃ������B���ہA�^���K���̂���l�͖Ɖu�@�\�����܂邽�߁A�a�C�ɂȂ�ɂ����A�^���K���̂Ȃ��l�ɔ�ׂĘV�����x���Ƃ���������܂��B
�ǂ̔N��ł��g�߂ɂł���^���ƌ����u�����v���ƁB�u�V���͋r����v�Ƃ�������悤�ɁA�r���g���^���͌��t�z�̑��i��S�g�̋ؓ����g�����Ƃɂ��Ȃ���܂��B
�T�ɐ���̃��N���G�[�V�������y�������̂ł��B����҂Ȃ�A�X�|�[�c�����łȂ���₨�m�Â��ƂȂǂ��C���]���ɂȂ�܂��B �܂��A���ԓ��m�ŏW�܂邱�Ƃ���݂ɂȂ�܂��B
�H�����̖ʂ�����A�h�{�o�����X�̂Ƃꂽ�H���͂������A����ی��p�H�i��h�{�@�\�H�i�Ō��N�̈ێ��Ƒ��i�ɖ𗧂����邱�Ƃ��ł��܂��B �H�ׂĂ��A�^���K��������A�����ƃJ�����[��������邱�Ƃ��ł��܂��B
�������A�^���̖ʂ�����H�����̖ʂ�����A�p�������邱�Ƃ����͕K�v�ł��B�������A���N�����g�܂Ȃ�����������ƁA�����������P�������Ƃ����ɖ߂��Ă��܂�����ł��B���X�̋x�e�͕K�v�ł����A�����������������邱�Ƃ��d�v�ł��B
����A�����オ��A�K�i����艺�肷��A�|�����ł���A��̎���ꂪ�ł���ȂǁA���������������ł���̗͂�����A�V��A���C�Ŋy������炵�Ă������Ƃ��ł��܂��B������ł��x������܂���B�����̂Ȃ����x���珙�X�ɉ^�����Ɏ�����Ă����܂��傤�B

| �̗͂𐊂������Ȃ��S���� |
|---|
| �G���x�[�^�[�E �G�X�J���[�^�[���K�i�𗘗p����B |
| �����X�s�[�h�𑬂߂�B |
| �Ƒ���C�̍������Ԃňꏏ�ɃE�H�[�L���O�A�X�|�[�c������B |
| �e���r�A�Ǝ��A�Ǐ������Ȃ���ł��ł���u�Ȃ���^���v���������B |
| �֎q�ɍ������܂܋r�𐅕��ɏグ��A�r�̓g���[�j���O�B�i�Б����j |
| ����Ŗ{�������Ȃ�����Ɏ�����������ؗ̓g���[�j���O�B |
| ���W�҂��̎��A�ܐ旧�����āA����̋ؗ̓g���[�j���O�B |
�@
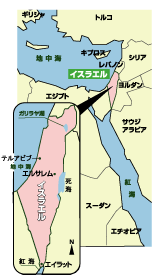
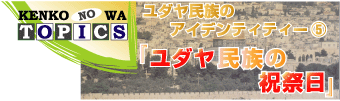
�Â̐����̎��ォ��A���j�ɖ������ރC�X���G���B�n���C�̓쓌���݈�Ɉʒu���鏬���ȍ��ł��B
���_���̐l�X�́A�Q�O�O�O�N�ɋy�ԗ��U�A�����Đ킢�̘A�����A�����̌ł��J�ŏ��z���A���c�̒n�C�X���G���ւ̋A�҂��ʂ����A�ߊ�ł������������������܂����B
�Ñ�ƌ��オ���a�����A�ٕ����̖��͂ɂ��ӂꂽ���A�C�X���G�������Љ�܂��B
�t�̗z�C�ɗU���āA�g�����ɐS��点��l�X���X�ɌJ��o���G���T�����B�X�����l�X�̑����́A�C�X���G�����O���痈�����_���̐l�B�ŁA�y�T�n�i�߂��z���̍Ղ�j�ƓƗ��L�O�����j�����߁A���E�e������W�܂��ė��܂��B�X�Ō��|���郆�_���l���O����b�����t�����Œ�`����͍̂���ŁA�������ɋ����Ń��V�A���b�����_���l������A�������ŃG�`�I�s�A���痈�����_���l�A�s�V���c�Ɣ��Y�{���ɃX�j�[�J�[�𗚂��싅�X�������c�A�����J�l�Ɍ����郆�_���l�����܂��B�������A�e�X�����_���l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�[�������A��ȋL�O�����j���Ƃ��������ړI�ɂ��A�C�X���G����K��Ă��邱�Ƃ�����A�����̌ւ�ƌł��J�������܂��B
���_���̐l�X���A���݂����j�Ɠ`����厖�Ɏ���Ă��鎖�́A�P�N��ʂ����j�Փ��̍s������������������Ƃ��o���܂��B
�܂��A���̗l�X�ȍs���́A�傫���R�ɕ��ނ��邱�Ƃ��o���܂��B
��P�̃O���[�v�́A�����Ɏ��ׂ��K�肳��Ă�����́B
��Q�̃O���[�v�́A�����ɋL���ꂽ�o�����A�܂��͌Ñ�̖����j�ɗR��������́B
��R�̃O���[�v�́A�ߑ�̗��j�̏o�����ɗR������L�O���ł��B
��P�̃O���[�v�ɂ́A�����ɂR��ՂƂ��ċL����Ă���Ղ肪����܂��B �G�W�v�g�E�o��A���_���������S�O�N�ɘj���čr�����Q���A�_�Ƃ��̗ƂƂ���������ÂсA�_�Ƃ⎩�R�Ɗ֘A���Đ��܂ꂽ�Ղ�ŁA�G�߂̐ߖڂɏj���܂��B�t�̃y�T�n�A�ẴV���u�I�b�g�i���T�Ձj�A�H�̃X�R�b�g�i�����̍Ղ�j�B�����̍Ղ�̓��ɂ́A�u�N�ɎO�x�A�j�q�͂��ׂāA��Ȃ�_�̌�O�ɏo�˂Ȃ�Ȃ��v�i�o�G�W�v�g�L�j�ƒ�߂��Ă��邱�Ƃ���A�R�叄��ՂƂ��Ă�Ă��܂��B���̑��A�V�N�ƃ����L�v�[���i���܍ߓ��j���܂܂�A���̃O���[�v�́A�ł����l�ŏ@���I�ȏj�Փ��Ƃ��āA�������Ɠ��l�ɘJ�����ւ����A�u�����v�Ƃ��Ĉ����܂��B
��Q�̃O���[�v�́A�����N�����o�ă��_�������̓`���̒��ɑ��Ղ������̂ŁA�����ɂ��K�肪�Ȃ��A���[�[�̗��@�Ƃ����W�A��Ђ��s�Ȃǂ��x�݂ɂȂ�܂���B ����A�������Ƃ������Ƃ���u�����ȏj�Փ��v�Ƃ��Ă�A�n�k�J�A�v�����A�e�B�V���E�x�A�u�Ȃǂ��w���܂��B �܂��A���[�V���E�z�f�V���i�����P���A���_����ŐV���̓��j�A���O�E�o�E�I�����A�g�D�E�r�E�V���o�b�g�i���̐V�N�j�Ȃǂ��܂߂邱�Ƃ�����܂��B
��R�̃O���[�v�ɂ́A�z���R�[�X�g�L�O���A�C�X���G���Ɨ��L�O���A�C�X���G����v�ҋL�O���A�G���T�����E�f�[�Ȃǂ�����܂��B���_�������̑S�̓I�ȋL�O���Ƃ������́A�C�X���G�����̍s���Ƃ����܂��B
| ��� | ���_���� ���� |
���� | �j�Փ��i2008�N�j | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ��P�� | 3���`4�� | �j�T�� | 30�� | 4��20���` 4��27�� |
�y�T�n�i�߂��z���̍Ղ�j |
| 5��2�� | �z���R�[�X�g�L�O�� | ||||
| ��2�� | 4���`5�� | �C���[�� | 29�� | 5��7�� | �C�X���G����v�ҋL�O�� |
| 5��8�� | �C�X���G���Ɨ��L�O�� | ||||
| 5��23�� | ���O�E�o�E�I���� | ||||
| 6��2�� | �G���T�����E�f�[ | ||||
| ��3�� | 5���`6�� | �V�o�� | 30�� | 6��9�� | �V���u�I�b�g�i���T�Ձj |
| ��4�� | 6���`7�� | �^���[�Y | 29�� | ||
| ��5�� | 7���`8�� | �A�u | 30�� | 8��10�� | �e�B�V���E�x�A�u�i2�̐_�a���� ���L�O����f�H���j |
| ��6�� | 8���`9�� | �G���[�� | 29�� | ||
| ��7�� | 9���`10�� | �e�B�V�����[ | 30�� | 9��30���` 10��1�� |
۰���Eʼ�Ű�i���ԋ��V�N�j |
| 10��9�� | �ѷ�߰فi���܍ߓ��j | ||||
| 10��14���` 10��20�� |
���āi�����̍Ղ�j | ||||
| 10��22�� | ��ʯāEİװ�i���@�̊���Ձj | ||||
| ��8�� | 10���`11�� | ��ͼ��� | 29�` 30�� |
||
| ��9�� | 11���`12�� | ��ڳ� | 29�` 30�� |
12��21���` 12��29�� |
�Ƕ�i�����Ձj |
| ��10�� | 12���`1�� | ��ޯ� | 29�� | ||
| ��11�� | 1���`2�� | ���ޯ� | 30�� | 1��22�� | ĩ��ް����ޯăg�i���̐V�N�j |
| ��12�� | 2���`3�� | ���� | 30�� | 3��21�� | ���сi�����̍Ղ�j |
| �[�� | ���٥���ư | 29�� | |||
![]()
![]()
