�N���X�^�j���E�h�i���G���̓������{�Ѓz�[���y�[�W
2008�N4����

�̂̂悤�Ȋ����ǂ�`���a�A�n���ɂ��a�C�͌����������̂́A�L���ł��낢��ȏ���m�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�������Љ�ł́A�V���ȕa�C��Ǐ��債�Ă���B
�v�������邱�Ƃ͂Ȃ����낤���B
����Љ�̒��łǂ���炷�H
�@�̑S�̂����ē����A�H�ו��������ɐH�ׂ��Ȃ���������ɔ�ׂ�ƁA���A���̒��͂����Ԃ�֗��ŖL���ɂȂ����B �Q�S���ԁA���ł��~�����Ƃ��ɐH�ו�����ɓ���A���ł��ǂ��ł��s���鎞��B
�@�������A���֗̕����ɊÂ��߂���ƁA�{���̌��N�I�ȑ̂̃o�����X������Ă��܂����ƂɂȂ�Ȃ����낤���B
�}���Ȍ���Љ�ւ̕ω��ɑ̂����čs�����A���ہA����a�ƌĂ��Ǐڗ��悤�ɂȂ����B
�@�l�Ԃ������Ă��錒�N�ɂȂ낤�Ƃ���͂����Ȃ���A�֗��ȎЉ�����ɐ����������Ƃ����C�ɉ߂����錍�ɂȂ�B
| �� �g�߂ɋN���錻��a �� | |
|---|---|
| �������K���a ����E���A�a�E�������� �����d���Ȃ� ���A�����M�[������ ���E�A�g�s�[���畆�� �����������ċz �nj�Q �����e頏� ���h���C�A�C �Ȃ� |
 |
| �����Љ�ɂȂ������̂́A�V���ɔ�������a�ɂ����銄���������B ���N�Ō��C�ȘV�㐶���𑗂肽���B |
 |
�L���ȐH�Ɩ����̉^��
�@�d����Ǝ��Ȃǂ̓s���Ŗ����A���܂������ԂɐH�����Ƃ�Ȃ�������A��y�ɐH�ׂ���C���X�^���g�H�i�⎉���̑�����������H�ׂ��肵�Ă��Ȃ����낤���B
�܂��A�Ԃ��g�������ĕ������Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ă��Ȃ����낤���B
�@�s�K���ȐH�����A�����H���A�^���s���Ȃǂ��璆�����b�����܂�A�������A�������ǁA�얞�A���A�a�Ȃǂ������N�������^�{���b�N�V���h���[���͗��h�Ȍ���a���B
�@�u�L���ȐH�v�Ƃ́A�h�{���L�x�ȐH���̂��ƁB
�X�֍s���ǂ�ȐH�ނł���ɓ��鎞��B
��𒆐S�Ƃ������낢��ȃ��j���[�ŁA�����̐H�����y���݂����B
�@�^���s���̉����͈ӎ������ĕ������ƁB�������Ƃ͒N�����C�y�ɂł���ȒP�ȉ^���@�B������ׂ�����Ȃ���A���y���Ȃ���A�����̊y���݂̈�Ƃ��Ă��ЁA���g��ŗ~�����B
���N���G�[�V�������ŃX�g���X����
�@�ߘJ��̂̍��g�Ȃǂ���A�S�ɂ��̂ɂ��X�g���X�������Ă���l�͑吨����B�ْ��^�̖������ɁA�ߕq�����nj�Q�A���a�Ȃǂ̓X�g���X�ƊW���[���ƌ����Ă���B
�@�X�g���X�Ƃ��܂��������Ă������Ƃŗ\�h���邱�Ƃ��ł��邪�A�Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ��̂��������B�����M���ł�����̂���������A���͂̐l�������|���ă��N���G�[�V��������N�[�[�V�����ɗU������C���]�����͂���S�������������B
�@�������A���a�̐l�ɗ�܂��͋֕��B�\���ȋx�{��^���A���R�ɐU�镑���Ɨǂ��B
���@�@���@�@��
�@�g�߂ɂ��錻��a�ɖڂ������Ă݂�ƁA���R�ɖh�����Ƃ��ł��邱�Ƃ���������B
���N����ɍl���A����Љ�ɏ��ɓK�����ĕ�炵�Ă������B

���n�n���̎��ォ��I�v�̎�����������ݑ����Ă������ב��ނ̍זE�̒��ɂ́A�l�ނ̌��N�ɂƂ��ėL�p�ȗl�X�Ȑ������܂܂�Ă��܂��B
����͐l�̂ɂƂ��ĕK�v�s���Ȑ����u�~�l�����v�����グ�܂��B
�~�l�����ɂ���
�~�l�����́A����ς����A�Y�������A�����A�r�^�~���ƕ��тT��h�{�f�̈�ł��B
�u����Ȃ��v�u�C���C������v�u�����������Ȃ����v�Ȃǂ̏ǏC�ɂȂ鎞�́A�~�l�����s����������������܂���B
�~�l�����͑傫��������ƁA�P���̐ێ�ʂ��P�O�O�r�ȏ�Ɣ�r�I�������̂���v�~�l�����A�����菭�Ȃ����̂���ʃ~�l�����ƌĂт܂��B
�����͍��v���Ă��A�̏d��̂P���`�Q�����ɂ����Ȃ�܂��A�s�������ꍇ�̌��N�ւ̉e���͑�ϑ傫���̂ł��B
��v�~�l�����Ƃ��āA��ʂɂ́A�J���V�E���A�}�O�l�V�E���A�J���E���A�i�g���E���A�����Ȃǂ��������A���ʃ~�l�����Ƃ��ẮA�N�����A�Z�����A�����A�}���K���A���A���E�f�A�S�Ȃǂ��������܂��B
�����̃~�l�����́A�l�Ԃ����N���ێ����Ă�����ŁA�ƂĂ���ȉh�{�f�Ȃ̂ł��B
| �y��w�I�ɔF�߂��Ă���~�l�������R�ǁz | |||
| �~�l���� | ���R�� | ||
|---|---|---|---|
| �� �v �~ �l �� �� |
�J���V�E�� | Ca | ���e頏� |
| �}�O�l�V�E�� | Mg | �S���a | |
| ���� | P | ������ | |
| �J���E�� | K | �s�����E�ؖ��͏� | |
| �� �� �~ �l �� �� |
�S | Fe | �S���R���n�� |
| �� | Cu | �n�� | |
| ���E�_ | I | �b��B�� | |
| �}���K�� | Mn | ������ | |
| �Z���� | Se | �S���a | |
| ���� | Zn | �E�сE�畆���� | |
| �N���� | Cr | �����l�̏㏸ | |
�ɒ[�ȉh�{�s�ǂ����������{�ł́A�d���a�C�ɂȂ�悤�� �~�l�������R�ǎ��̂����Ȃ��Ȃ����B
�~�l�����̖������S
�̂̒��ɁA�~�l�������\�������Ă��A��͂�o�����X����ɂȂ�܂��B�Ⴆ�A���B�̑̂�����Ă���זE�͂U�O������ƌ����Ă��܂����A�~�l�����͍זE�̒��ƊO�ł͈قȂ��Ă���̂ł��B
�J���V�E����i�g���E���́A��ɍזE�̊O���ɂ���A�זE�̓����ɂ̓}�O�l�V�E����J���E�������݂���̂ł��B�זE�̒��ƊO�Ńo�����X���ۂ���Ă���A���ꂼ�ꂪ�s�����Ă��܂��ƁA�זE�̓����Ȃǂ��ቺ���Ă��܂��̂ł��B
���ƃ~�l����
��ʂɍ��̌��N�ƌ����ƁA�N�����J���V�E����z������Ǝv���܂����A����ۂ��Ă���̂́A�J���V�E���̑��ɁA�}�O�l�V�E���A�����A�i�g���E���A�����������Ă���A���̂T��ނ��o�����X�悭�݂��Ɏx�������Ă���̂ł��B
�J���V�E���������\���ɑ��݂��Ă��A�}�O�l�V�E���∟���Ȃǂ��s������A�����キ�Ȃ��Ă��܂��̂ł��B
�܂��A�זE�O�̃J���V�E�����s�����Ă��܂��ƁA������J���V�E�����n���o���ĕ₨���Ƃ��܂��B����ƁA������}�O�l�V�E���A�������ꏏ�ɗn���o���Ă��܂��̂ł��B
�ł�����A���̌��N��ۂɂ́A�J���V�E���������l����̂ł͂Ȃ��A�S�̓I�ȃ~�l�����o�����X���l���鎖����Ȃ̂ł��B
�s����X�g���X�A�s���ƃ~�l�����̊W
�}�O�l�V�E���́A�S����ؓ��̓����������鎖���m���Ă��܂����A������_�I�Ȗʂɂ����Ă��A�ƂĂ��d�v�ȃ~�l�����Ȃ̂ł��B
�}�O�l�V�E���́A�������^�����邱�ƂŁA����A����r�o����₷���Ȃ�A�s���������ȃ~�l�����̈�ł��B
�܂��A�X�g���X������ɂ���Ă��s���������ɂȂ�̂ŁA�J���V�E���Ƌ��ɐێ��S�����܂��傤�B
���t�ƃ~�l����
���⎉���̑�ӂɌ������Ȃ��~�l�������N�����ł��B���Ɍ������R���g���[������C���X�����̓����𐳏�ɕۂ��߂ɕK�v�ƂȂ�܂��B
�܂��A���t�ɐ[���ւ���Ă���̂��S�ł��B�S�͕n����\�h������A�S���̖Ɖu�͂��������铭��������A�Ԍ����̃w���O���r�������h�{�f�ł�����̂ł��B
�ߔN�͏����̂R�l�ɂP�l���n���ł���ƌ����A�S�s���̐l�������Ă��܂��B �����ȃ_�C�G�b�g��C���X�^���g�H�i���悭�H�ׂ�l���S�����s���������ł��B
�R�[�q�[�̃J�t�F�C����Β��̃^���j���Ȃǂ͓S�̋z����W���܂��̂ŁA���ʓI�ȋz����S������ۂɂ́A�Q�l�ɂ��Ă��������B
�َ��̔��琬����j���@�\�̐��퉻��
�̂̒��ł́A�����������ێ����邽�߂ɁA�ƂĂ������̍y�f����ӂ��s���Ă��܂��B
�����͂���ς����̍�����C���X�����Ȃǂ��͂��߁A��R�O�O����̍y�f��������������̂ɖ𗧂��܂��B
���ɍזE����𐳏�ɍs�����Ƃʼn��ǂ⏝�̉���������A�j���@�\�𐳏�ɐ�������A�َ��̐�����������Ȃǂ̓���������܂��B
�R�_���A��łƃ~�l����
�̘̂V����h������A�̓��̗L�Q������r�o����̂ɏd�v�Ȃ̂��Z�����ł��B
�Z�����͂��ꎩ�̂��R�_����p�������߁A�V���\�h�ɂ͂ƂĂ��𗧂��܂��B�܂��A�r�^�~�����-�J���`���Ȃǂ̍R�_�������ƈꏏ�ɐێ悷��Ƃ����ʓI�ł��傤�B
�܂��A�J�h�~�E����q�f�A����Ȃǂ̗L�Q�����Ƒ̓��Ō��т��A���̓Ő����キ���Ă���铭��������̂ł��B�̑���ی삵�Ă����Ƃ���������܂��B

�����̃~�l�����́A�C���ɑ����܂܂�܂����A�����̍ۂɎς邱�ƂŁA����o�Ă��܂����Ƃ������̂ł��B ��ȃ~�l�����������悭�ێ�ł���悤�A�Ϗ`�܂ł�������H�ׂ�悤�ɐS�����܂��傤�B
���ב��ނɂ��~�l�������ɕx��ł�����̂������̂ŁA�r�^�~���ƈꏏ�Ƀo�����X�悭�ێ悷�邱�Ƃ�S�����܂��傤�B
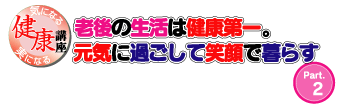
����҂̌��N���Ⴂ������S�����Ă����܂��傤�B
�������A��{�I�Ȑ����K����g�ɂ��Ă������ƁA�ϋɓI�ɉ^�����s�����ƁA�N��ɉ������H���̐ۂ���ȂǁA�C�t�����Ƃ��Ɏ��s����Ό��C�ȘV�オ�����ł��傤�B
��̓I�ȓ��e�����Љ�܂��B
�C�t���������n�߂ǂ�
��������̔N��͑̂������߂ɁA���G�l���M�[�̐H����ؗ͂ɕ��ׂ������đ̗͂����߂邱�Ƃ�����܂��B�������������Ă������ɂ͌��C�ɉ��邱�Ƃ�����܂��B
�Ƃ��낪�A����ɂȂ�Ɖ���ɔ����A�g�̓I�A���_�I�A�V��ӂȂNj@�\�̌��ނ��N���܂��B�Ⴂ���Ɠ����悤�ɖ����Ȑ��������Ă���ƁA�̒���������ƂɂȂ�ł��傤�B
������ƌ����āA�Ⴂ���̖�������������������ł��傤�B�J�����[�̐ۂ�߂��₽���̋z���߂��Ȃǂ́A�K���ɂȂ��Ă��܂��A�Ȃ��Ȃ���߂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�����āA�Ⴂ�Ƃ��͑̂ɕω�������Ȃ��Ă��A�J�����[�ێ��i���̒~�ς͌����Ȃ��Ƃ���ő̂ɕω��������炵�Ă��܂��B�C�t�������ɂ͂������K���a�ɂȂ��Ă����Ƃ������Ƃ����Ȃ�����܂���B
�����ɑ������e頏ǂ������B�o��A�����x���ቺ���Ă��܂��̂ŁA����܂łɍ����x�����߂Ă����K�v������܂��B
�_�f���̓��ŃG�l���M�[�ɕω����鎞�Ɂu�����_�f�v�Ƃ����V����a�C�̌��������o���Ă��܂��B�����_�f�͂���ς�����c�m�`�������A����A�����d���A�畆�̂��݂₵��Ȃǂ̂��܂��܂ȏǏ�������܂��B
���̂��߁A�Ⴂ�����犈���_�f�������Ă����A������}���Ă������Ƃ���B�����_�f�̏����ɂ̓r�^�~���ށA�t���{�m�C�h�ށA�~�l�����ނȂǂ̉h�{�f���K�v�ɂȂ�܂��B
�N��ɉ������J�����[�A�h�{��ނ̑��ʂȐH����S�����邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�̂ł��B
�H���Ɖ^��
�ł́A��̂ǂ�ȐH����ۂ�Ηǂ��̂ł��傤���B
�h�{�L�x�ȓ��e�͂������A�̂̕ω���a�C�̏Ǐ�ɉ����������@�ɂ��C�Â������ƂŌ��N��ۂ��Ƃ��ł��܂��B
�R�_���H�i�Ƃ��ẮA�Ή��F��A���ؗށA�C���ށA���܁A�哤�A���A���k�ނȂǂ������߁B ����ɂȂ�ƃG�l���M�[�ێ�ʂ͌������܂����A����ς����A�r�^�~���A�~�l�����̐ێ�ʂ͌��������Ă͂����܂���B ���������Ӗ��ł��A�����̐H�i�͔N��ɂ�����炸�A�ϋɓI�ɐۂ��Ă����������̂ł��B
�֔�\�h�ɂȂ�H���@�ہA���H�𑝂₷���Ƃ��ł���ۑ��H�̗��p�A�H�~�i�����鏭�ʂ̃A���R�[�����������H�v���ǂ��ł��傤�B
�����āA�y�����H�������邱�Ƃ��d�v�B �Ƒ���F�l�Ƃ̌𗬂����˂āA���������H����ۂ�܂��傤�B
���퐶���ł́A�H�ׂ邱�ƂƓK�x�ȉ^�����K�v�ł��B�H�~���i�A�얞�\�h�A�ؗ͒ቺ�̖h�~�A���e頏ǂ̖h�~�Ȃǃ����b�g����������܂��B
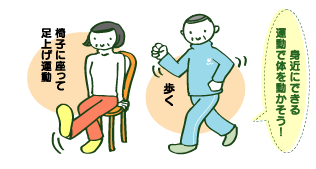
�E�H�[�L���O�͒N���������n�߂���^���B �֎q�ɍ����āA�G���𐅕��ɏグ��������ȂǁA�y���ؗ͑̑����ǂ��ł��傤�B ����̉^�������łȂ��A���ɂ̓X�|�[�c���y���ނƁA�C�������t���b�V�����܂��B
�������A�������X�|�[�c��̗͂������Ղ���X�|�[�c�͉^���\�͂��ቺ���Ă���l�ɂ͊댯�Ȃ̂ŁA�N��ɊW�Ȃ��A�N�����y���߂郌�N���G�[�V�����Ƃ��āu�j���[�X�|�[�c�v�͂������ł��傤���B
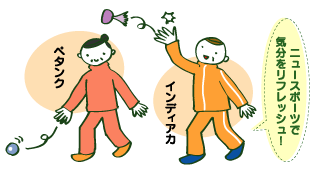
�j���[�X�|�[�c�̓��[�����ȒP�ŁA�q�ǂ�����Q�҂��Q���ł���X�|�[�c�ł��B ���̂��߁A���ƈꏏ�Ƀ��N���G�[�V�������y���ނ��Ƃ��ł���̂ł��B
�������܂��͖ؐ��̃{�[�����R�[�g�ɓ����ē_�������������u�y�^���N�v��A�Ԃ��H������������Ȕ����{�[������őł������u�C���f�B�A�J�v�Ȃǂ��L���ł��B
�e�n�̎����̂Ȃǂł��ϋɓI�ɑ���Q���C�x���g���s���Ă���̂ŁA��x�A���w����Ɨǂ��ł��傤�B
����҃C�x���g�ɎQ�����悤
��N���}������A���̐l�����ǂ̂悤�ɂ��ĉ߂��������l�������Ƃ͂���܂����B �ߔN�A�c��̐��オ������N���}���邱�Ƃ������āA����Ҍ����̃C�x���g�A�u���A���U�w�K����葽����������悤�ɂȂ�܂����B ��قǂ̃j���[�X�|�[�c���������ł��B
�u�R�E�u���v�̂悤�ȁA��Ћ߂ł͂Ȃ��Ȃ����Ԃ����Ȃ������A�g�߂ȐA���ɖڂ����������U�w�K�ɐl�C�����܂��Ă��܂��B �u�j�̂��߂̗����u���v�̂悤�ɁA�ƒ�Ŏ����ł���j����Ǝ��ɂ��ϋɓI�ɎQ���ł���j����ڎw���u�����J����邱�Ƃ�����܂��B
���������C�x���g�͔���퐶���𖡂킦�A���낢��Ȑl�Ƃ̏o�������܂��B��������ւ��L����A�����̂��߁A�䂭�䂭�͒n��̂��߂ɂȂ��Ă����͂��ł��B
�Ƃ̒������ɕ������炸�A�ǂ��h�����邱�ƂŁA���C�͂�Ƃ��������𑗂�܂��傤�B
�Q�l�����^������̕a�C�ƐH���i�㎕��o�Ŋ�����Ёj�A
����҈�Ãn���h�u�b�N�i���o���f�B�J���J���j�A
��N�w�i�u�k�Еҁj
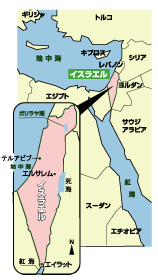
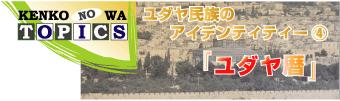
�Â̐����̎��ォ��A���j�ɖ������ރC�X���G���B
�n���C�̓쓌���݈�Ɉʒu���鏬���ȍ��ł��B
���_���̐l�X�́A�Q�O�O�O�N�ɋy�ԗ��U�A�����Đ킢�̘A�����A�����̌ł��J�ŏ��z���A���c�̒n�C�X���G���ւ̋A�҂��ʂ����A�ߊ�ł������������������܂����B
�Ñ�ƌ��オ���a�����A�ٕ����̖��͂ɂ��ӂꂽ���A�C�X���G�������Љ�܂��B
���E�ɋ��ʂ���N���ł��鐼��B�I���O�͂a�b�iBefore Christ�j�A�I����͂`�c�iAnno Domini�E�w��̔N�Ɂx�̈Ӂj�Ɨ����Ďg���܂����A����́A�L���X�g���a�̔N����O��ɐ����Ă����܂��B ����䂦���A���_�����k�͂a�b��`�c���g�킸�A�b�d�iCommon Era�w���ʗ�x�j���N�ƌ�������A�I���O���a�b�d�iBefore Common Era�j�Ƃ����������g���܂��B
���_���̎Љ�ł́A���퐶���͐���A�@���I�ȏj�Փ��Ȃǂ́A���_�����Ǝ��́w���_����x�ɂ���čs���܂��B ���_����́A����ɂR�V�U�O�N���������N���ɓ������A�����Ɋ�Â��A�V�n�n���̔N�i�n���I���j���P�N�Ƃ��Čv�Z�����N�����̗p�������̂ł��B�����ɂ��A���_�������̋����ɑ����ΓI�Ȏp���ƌւ�������邱�Ƃ��o���܂��B
�������u�P�����v���A�V�����玟�̐V���܂ł̂Q�X�����R�O���̎��ԂƂ����w���A��x�A�����āA�n�������z���P�����鎞�Ԃ��u�P�N�v�Ƃ���w���z��x�B ���A��P�Q�����Ƒ��z��̊Ԃł́A�P�N�ɂ��P�O���`�P�P���̌덷�������A�t�̖K��������錎���A���̋G�߂����̊Ԃɂ��O��Ă��܂��ȂǁA���퐶���ɂ����Ă��s�s���������邱�Ƃ������Ȃ�܂��B
�����ŁA���z��ɂ���āA���܂��������ꂽ���_���l�̑��A��A���_����Ƃ��ďo���オ��܂����B �ʏ�P�N�Ԃ̓����́A�R�T�R�`�R�T�T���ɂȂ�̂ł����A�o�����X���Ƃ邽�߂ɁA�P�X�N�ԂɂV��̉[�N��݂��A�[�N�ɂ͉[�����������P�R�������P�N�Ƃ��ē����߂��܂��B �܂�A���̉[�N�̓������R�W�R�`�R�W�T���ɂȂ�A�s����������₤�`�ɂȂ��ł��B
��������̌����́A�{���A��P���A��Q���Ɛ����Ő������Ă��܂����B�����āA�j�T������V�N�Ƃ���t�N�������̗�ł������A�Q���I�Ȍ�A�e�B�V�����[���Ɏn�܂�H�N�i�_����j�ɕς��A����ł����X������P�O�����V�N�ƂȂ�܂����B �܂��A�C�X���G�����̌����s���́A���_��������ƂɎ���s���邱�Ƃ���A�P�X�S�W�N�T���P�S���̓Ɨ��錾���A���_����ł́u�T�V�O�W�N�C���[�����T���v�ƂȂ�܂��B ���ׁ̈A���̂悤�ȓƗ��L�O���Ȃǂ͖��N�A����ɂ���ƈقȂ������t�ɂȂ�܂��B
���퐶���ɂ����ẮA���_���l��������g�p���܂��B�C�X���G���̉p���V���ɂ́A �P�X�X�W�N�Z�v�e���o�[�c�Ƃ�������ƁA �T�V�T�W�N�G���[�����c�Ƃ������_������L����Ă��܂��B �܂�����́A�w�u���C��̌��̖��O���p��̖|��ɋ߂��A��ʓI�ɂ͂P�������k�A���A�Q�����t�F�u���A���ȂǂƌĂ�ł��܂��B
| ��� | ���_���� ���� |
���� | �j�Փ��i2008�N�j | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ��P�� | 3���`4�� | �j�T�� | 30�� | 4��20���` 4��27�� |
|
| ��2�� | 4���`5�� | �C���[�� | 29�� | 5��2�� | |
| 5��7�� | |||||
| 5��8�� | |||||
| 5��23�� | |||||
| 6��2�� | |||||
| ��3�� | 5���`6�� | �V�o�� | 30�� | 6��9�� | �V���u�I�b�g�i���T�Ձj |
| ��4�� | 6���`7�� | �^���[�Y | 29�� | ||
| ��5�� | 7���`8�� | �A�u | 30�� | 8��10�� | �e�B�V���E�x�A�u�i2�̐_�a���� ���L�O����f�H���j |
| ��6�� | 8���`9�� | �G���[�� | 29�� | ||
| ��7�� | 9���`10�� | �e�B�V�����[ | 30�� | 9��30���` 10��1�� |
۰���Eʼ�Ű�i���ԋ��V�N�j |
| 10��9�� | �ѷ�߰فi���܍ߓ��j | ||||
| 10��14���` 10��20�� |
���āi�����̍Ղ�j | ||||
| 10��22�� | ��ʯāEİװ�i���@�̊���Ձj | ||||
| ��8�� | 10���`11�� | ��ͼ��� | 29�` 30�� |
||
| ��9�� | 11���`12�� | ��ڳ� | 29�` 30�� |
12��21���` 12��29�� |
�Ƕ�i�����Ձj |
| ��10�� | 12���`1�� | ��ޯ� | 29�� | ||
| ��11�� | 1���`2�� | ���ޯ� | 30�� | 1��22�� | ĩ��ް����ޯăg�i���̐V�N�j |
| ��12�� | 2���`3�� | ���� | 30�� | 3��21�� | ���сi�����̍Ղ�j |
| �[�� | ���٥���ư | 29�� | |||
![]()
![]()
