クロスタニン・ドナリエラの日健総本社ホームページ
7.マイクロアルジェ採集
イスラエル2000大研修視察団の大きな目的のひとつが、自らの手で、マイクロアルジェを採集し、人類に有用性のあるマイクロアルジェを見出す可能性に一歩近づくこと。
今回は、4班がイスラエル国内4箇所にて採集。
心弾ませた出発の日、受付カウンターでしっかり手渡されたマイクロアルジェ採集の小道具が、いよいよ出番を迎えます。
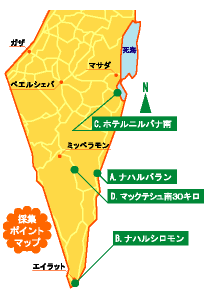
A班はナハルパラン、B班はナハルシロモン、C班はホテルニルバナ南、D班はマックテシュ南30キロ。イスラエル国の南半分にすべてのポイントがあり、各班とも、厳しい砂漠地帯の中で増殖できる、より生命力の強い、貴重なマイクロアルジェを採集したことになります。
未だ、確認されていない微細藻類(マイクロアルジェ)は、数万種以上存在すると言われており、今回の採集で新種が発見される可能性も十分あります。
■C班 ホテルニルバナ南
ドナリエラが発見された死海での採集ということもあり、新種発見の期待を込めて作業に取り組むC班。思わず採集の手を止めるほどの美しい死海が目前に迫ったこの場所は、土の塩分濃度が高いのが特徴。新しいマイクロアルジェが誕生するかもしれません。


 |
 |
自分なりの狙いを定めて、 採集スコップを土の中に入れる。 |
■A班 ナハルパラン
ヨルダン国境付近のこのポイントの特徴は、D班に似て、乾いた砂漠地帯。採集の音頭をとるのは、微細藻類学者の中野武登先生。強い味方を付けたA班は、例え国境付近であっても、必ずマイクロアルジェ採集を成功させたい強い意志で、硬い土をスコップで掘り起こし、新種の獲得に夢をふくらませました。
 |
 |
 |
||
| 土表面から5cm下にマイクロアルジェが潜む可能性が高い。 | ||||
■D班 マックテシュ南30キロ
結団式で、松浦販社長より『日本へ帰ったら、採集したシャベルを飾り、とにかく、多くの人にシャベルことが大切』との言葉をいただき、採集することと、伝える使命に燃えたD班。乾いた砂漠のまん真ん中に点在する同志たちは、それぞれが一生懸命、作業に取り組んでいました。
 |
 |
|
| 「草の生えたところに、マイクロアルジェが隠れているかも」 皆、楽しそうに探索しながらの採集。 |
||

■B班 ナハルシロモン
今回の研修視察団によるマイクロアルジェ採集4ポイントの最南端の地が、B班の採集ポイント地であるエイラット。「N.B.T.があるこの場所で、ぜひ、新しいマイクロアルジェに出会いたい」。グループ同志たちの思いは、この地の微細藻類に届いたでしょうか。
砂漠といっても、大きなユーカリの木が力強く育つオアシスもあり、マイクロアルジェの生息も期待できそうです。
 |
 |
 |
||
 |
木陰のオアシスめざしての採集。 |
